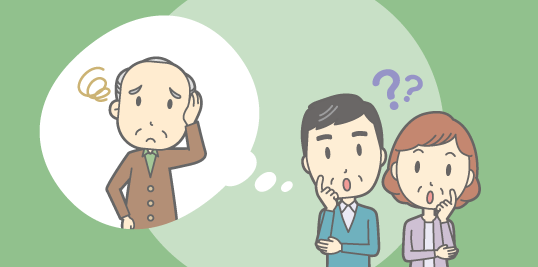認知症と医療行為への同意の問題(2)
「認知症と医療行為への同意の問題」という記事の続編です。
前編では,「どのような治療を受けるのかということは、高齢の患者さんであっても、本人の意思が優先して判断されます。
本人の判断能力が十分ではない場合であっても、『本人ならばこの状況でどのような選択をするか』ということを軸として判断がされ、家族等が代理して判断することはできません」とされています。家族等がこの「判断」を求められたときも深刻な問題が生じますが,さらに深刻であるのは「判断」を求められるのが成年後見人,それも親族ではない専門職(弁護士,司法書士又は社会福祉士)の成年後見人である場合です。
このような場合における成年後見人による判断の当否を定めた法規は存在しません。
法規がない以上、緊急避難,緊急事務管理その他の一般条項やさらには条理の解釈によって判断の当否を定めるほかありません(『新成年後見制度の解説【改訂版】』(きんざい,平成29年)153頁)。
そのため,厚生労働省が定めるガイドライン(令和元年6月3日「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」27頁においても,
※医療機関としての留意点
現行制度では、成年後見人等の役割としていわゆる医療同意権までは含まれないことについて十分留意し、成年後見人等に同意書へのサインを強要することがないよう注意して下さい。
医療機関が成年後見人等に対して説明を行った旨を、医療機関と成年後見人等の間で事実確認として残したい場合には、例えば『成年後見人として担当医の説明を受けました』等の記載とすることで対応するという方法もあります」
とされるにとどまり,同意権は存在しない,すなわち判断の当否はわからない,ということが前提になっています。
しかし,「わからない」ということは予見可能性を欠くということであり,予見可能性を欠くということは,治療を行う医療機関側も,判断を求められる可能性がある成年後見人側も訴訟リスクに晒されることを意味します。
そのような訴訟リスクが現実のものとなる前に,国会によって法規を定める立法的な解決が望まれます。
 |
作成:中尾法律事務所 弁護士 中尾 太郎
大阪弁護士会所属。同会高齢者・障害者総合支援センター 介護福祉部会長。 |